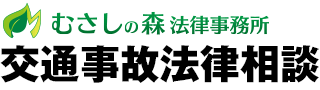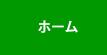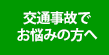遷延性意識障害(植物状態)の20歳女子の被害者に改善効果をもたらしたDCS(脊髄後索電気刺激)療法の必要かつ相当性を認めた判決です。
DCS療法(脊髄後索電気刺激療法・脳や末梢脊髄を刺激し,意識の賦活,除痛,筋緊張緩和法等を目的とする療法)
を遷延性意識障害を負った20歳女子が植物状態を脱却する一定の効果を及ぼし,被害者の治療として相当であったと,DCS療法と本件事故との相当因果関係を認めた判決です。
大阪地裁 平成19年2月21日判決(確定)
<出典> 自動車保険ジャーナル・第1695号(平成19年7月19日掲載)
被害者(当時,20歳女子大学生)は,乗用車を運転し車線変更中に,酒気帯びで運転中の乗用車が第1車線から車線変更してきて左後部に衝突,導流帯に駐車していた普通貨物車に衝突して事故となりました。
被害者は脳挫傷等から遷延性意識障害(いわゆる植物状態)となり,531日入院し,1級3号後遺障害を残しました。
脳や末梢脊髄を刺激し,意識の賦活,除痛,筋緊張の緩和を目的とするDCS療法(脊髄後索電気刺激療法)が,被害者には,「必要かつ相当なものであった」かどうかが争点となりました。
DCS療法に関する部分に絞っています。
被害者は,平成14年2月22日にDCS療法を開始後,同年3月以降,従命反応が向上し,部分的に経口摂取が可能となり,上肢の動きが向上し,同年4月下旬には,手指を用いて若干の意思表示ができるようになったものであり,同年6月19日の退院時までに各方面で症状が改善し,状態・反応スケール及びグラスゴーコーマスケールによるスコアがいずれも向上したことが認められる。
DCS療法の作用機序は,必ずしも解明されていないものの,被害者は,若年であること,頭部外傷によって植物状態となったこと,植物状態となってから長期間が経過していないこと等DCS療法実施後に改善が見られた症例に多く見られる条件を満たしており,被害者に現に前記のような改善が見られたことからすると,DCS療法が被害者の症状に対し,効果があったと認めるのが相当である。
加害者側は,外傷性の脳機能障害を負った若年の患者については,外傷を受けてから長期間が経過していない場合,DCS療法を行わなかったとしても,自然経過あるいは介護を行う近親者に対するプラシーボ効果により,症状に一定の改善が見られる可能性があると主張し,医師による同旨の意見書を提出する。
しかしながら,被害者は,本件事故後,約7か月間の治療を経ても,自己開眼はするが,追視,従命反応がない状態であったのに,DCS治療開始後の約2か月間で簡易な意思表示が可能になったものであり,DCS療法開始前において医師が被害者の症状につき,大きく改善する見込みはないという見通しを有していたことに照らせば,前記の症状の改善が自然経過によるものであるとは考えにくいし,被害者春子や被害者太郎がDCS療法の効果に期待して被害者の介護を従前以上に熱心に行うことがあったとしても,そのことが前記のような改善をもたらすと考えることは困難である。
以上より,実施されたDCS療法は,被害者の症状に対し,一定の効果を及ぼしたものと認められ,同病院及びJ病院において行われた治療は被害者の傷害及び障害の治療として必要かつ相当なものであったというべきであるから,これらに要した費用についての損害の発生は,本件事故との間に相当因果関係があるというべきである。
脊髄後索電気刺激療法(DCS療法 Dorsal Column Stimulation)は,1967年により開発された除痛術の一種で,脳深部電気刺激法(DBS deep brain stimulation)に類似したものです。
それに改良を加えて遷延性意識障害の治療にも応用されています。
1999年に日本でも完全体内植え込み型装置が導入されました。
頸髄背側に挿入した電極から電気刺激を加えることにより,脳や末梢脊髄を刺激し,意識の賦活,除痛,筋緊張の緩和を図る治療法であり,心臓ペースメーカーを改良した受信機の電極を第3ないし第5頸椎から脊柱管内に入れ,第2ないし第3頸髄背側の硬膜上に挿入することによって行うとされています。
電気刺激の制御は,外部の送信機から,受信機のアンテナを介して,指令を発することにより行い,電気刺激を毎日昼間の6ないし12時間にわたり,持続的に与えます。
作用機序は明らかではありませんが,現在では遷延性意識障害に対して賦活系の刺激,脳血流増加,カテコールアミン代謝の賦活作用が関与して一定の効果があるとされています。