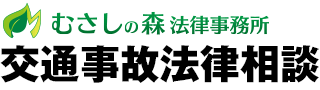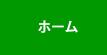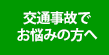個人事業者が過少申告であったものの実態などから賃金センサスを基礎収入として休業損害等を算定した判決です。
建設業者(男・事故時53歳,14級9号)につき,事故前3年の申告所得額は,収入金額に比して低額に過ぎ,到底現実の生活水準が維持できないと認められるものでした。
そして,従業員10数名を雇用して個人で建設業を営んでいたことから,賃セ男性学歴計50歳から54歳平均687万5000円を基礎収入とし,事故後半年間の売上は前年同期と比較して35.5%減少していることから,症状固定まで35.5%の減収と認めました。
大阪地判平成20年3月11日
交民集41巻2号283頁
被害者である原告は,次の通り主張しました。
原告は,10数名の従業員を雇用して,C鉄筋工業の屋号で,鉄筋橋脚組立工事の第二次あるいは第三次下請を行っていた。
しかし,本件事故による受傷によって,現場において陣頭指揮をとることができなくなったことから,本件事故後半年間(平成18年7月から平成18年12月)の売上の実額は1,915万4,196円,経費の実額は1,637万2,247円となり,その差額である実収入額は278万1,949円となった。
原告の,前年同期の売上の実額は2,972万6,010円,経費の実額は2,330万7,479円であり,その差額である実収入額は641万8,431円であったので,原告の実収入は,本件事故によって363万6,482円減少したことになる。
その収入の減少は,平成18年下半期の部分に限られるところ,原告は,本件事故によって,本件事故の翌日である平成18年6月23日から症状固定日である平成19年2月9日まで稼働することができなかったため,上記期間中の休業損害は,少なくとも454万5,602円となる。
これに対して,加害者である被告は,次の通り反論をしました。
原告は,本件事故による傷害によって現場で陣頭指揮をとることができなくなった旨主張するが,原告が,その主張する休業期間中に,現実に稼働していなかったか否かは定かではない上,原告の従業員は,本件事故の前後を問わず,就労しているのであるから,原告には不労所得が発生しており,原告の主張する収入の全額を,原告の休業損害とすることはできない。
また,原告の本件事故前後の6か月間の売上を比較すると,大差はなく,減収の事実は認められない。
さらに,原告は,確定申告に際して,経費を実際よりも多額に計上していた旨主張するが,原告の提出した証拠のみから,そのような事実が裏付けられることにはならない。
原告は,各確定申告に際して,収入金額等については,実際の収入額を申告しながら,経費については,特に「外注工賃」について,実際に生じた費用を超える額を計上する等して,いわゆる過少申告を行っていたことが,それぞれ認められる。
そして,原告の実収入に関する上記主張は,公的な裏付けを欠いており,これをそのまま採用するわけにはいかない。
しかしながら,他方,少なくとも平成17年における原告の営業収入(売上)の入金は,全て銀行振り込みによって行われていることが認められ,この額は,上記平成17年の所得税の確定申告書等に記載された「収入金額」と一致しているところ,上記各確定申告書等の「所得金額」欄に記載された額は,収入金額に比して低額に過ぎ,このような額では,到底,現実の生活水準が維持できないとみられる上,前記認定のとおり,原告は,従業員10数名を雇用して個人で建設業を営んでいたというのであるから,これら諸事情に照らせば,本件事故当時の原告個人の上記事業による収入は,平成18年賃金センサス・産業計・企業規模計・男性労働者・学歴計・50歳から54歳の平均賃金である687万5,000円と同程度であったとみるのが相当である。
一般に,事業所得者の基礎収入に関しては,事故前の申告所得額を採用し,いわゆる固定経費を支出していれば,これを加算するというのが裁判所の基本的な考え方です(八木・佐久間 交通損害関係訴訟 青林書院 P141)。
本件判決では,被害者である原告が過少申告をしていた事実を裁判所は認めて,その上で,その申告額によらずに基礎収入額を認定しています。
しかし,原告が主張する「本件事故後半年間(平成18年7月から平成18年12月)の実収入(売上額と経費との差額)」による主張については,否定しています。その上で,原告の営業収入(売上)の入金は,全て銀行振り込みによって行われており,その金額が例えば平成17年の所得税の確定申告書等に記載された「収入金額」と一致している事実を重視しています。
つまり,売上については,すべて銀行振り込みで行われており,税金申告において,その点での不正らしさはなく,経費等の操作によって,結果として過少申告になっていると言うことです。その上で,実態等から,少なくとも,賃金センサスによる平均賃金は認めるというのが判決の考え方です。